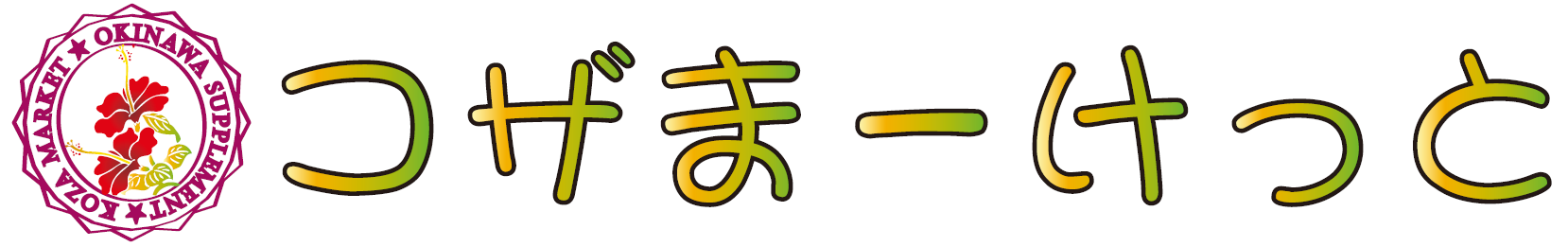非常食を備蓄する必要性
地震や台風、豪雨などの自然災害は、いつどこで発生するかわかりません。電気やガス、水道といったライフラインが途絶えてしまうと、通常の食事を用意することが難しくなります。そのため、あらかじめ非常食を備蓄しておくことが、家族の命と健康を守る大切な手段になります。特に日本は災害が多いため、日頃から備えを整えておく意識が重要です。
非常食備蓄の基本ルール
非常食を準備する際には、単に保存できる食品をそろえるだけでは不十分です。家族構成や生活習慣に合わせて、必要な量や種類を考えることが求められます。
備蓄する日数の目安
一般的には最低3日分、できれば1週間分の非常食を用意すると安心です。大規模災害では物流が止まり、支援物資が届くまでに時間がかかるため、余裕を持った備蓄が推奨されています。
1人あたりの食料と水の量
食料については1日あたり3食分を基本に計算します。また、水は調理用も含めて1人あたり1日3リットルが目安です。飲料だけでなく、簡単な洗浄やうがいにも必要となるため、多めに確保しておきましょう。
備蓄に適した非常食の種類
非常食にはさまざまな種類がありますが、保存性や調理のしやすさを重視することが大切です。また、普段から口にしているものを中心にそろえると、いざというときにも食べやすくなります。
主食になる食品
・アルファ米(お湯や水を注ぐだけでご飯になる)
・インスタント麺や乾麺
・クラッカーやビスケット
これらは腹持ちがよく、エネルギー補給にも役立ちます。
おかずや副菜になる食品
・缶詰(魚、肉、豆類など)
・レトルト食品(カレーやスープ類)
・フリーズドライの野菜や味噌汁
調理不要で食べられるものが多く、栄養バランスを整える助けになります。
おやつや栄養補助食品
・チョコレートやキャンディ
・栄養補助食品やエナジーバー
甘いものはストレスを和らげる効果もあり、子どもや高齢者にも喜ばれます。
備蓄を長持ちさせる工夫
非常食を備えるだけでは、賞味期限切れになってしまうことがあります。そのため、ローリングストックという方法を取り入れるのがおすすめです。
ローリングストック法とは
日常的に非常食を食べ、食べた分を買い足す方法です。常に新しい状態の食料が備蓄されるため、いざというときに古くなった食品を使う心配がありません。
賞味期限の管理方法
・食品ごとに賞味期限をメモして一覧化する
・収納場所に早く使う順番で並べる
・半年ごとに点検する習慣をつける
こうした工夫で、無駄なく備蓄を続けることができます。
家族構成に合わせた工夫
非常食の備蓄は、家族の年齢や健康状態に応じた工夫が欠かせません。小さな子どもや高齢者、アレルギーのある人などに配慮することが大切です。
子ども向けの配慮
食べ慣れた味ややわらかい食感のものを選ぶと安心です。ミルクやお菓子類も準備しておきましょう。
高齢者向けの配慮
噛む力が弱い方にはやわらかい食品やゼリータイプのものがおすすめです。塩分や糖分の摂取量も考慮してください。
アレルギー対応食品
アレルギーを持つ家族がいる場合、原材料表示をよく確認して準備します。小麦や乳製品を使わない非常食も販売されているため、安心して備蓄できます。
まとめ
非常食の備蓄は、家族を守るための大切な準備です。最低でも3日分、可能であれば1週間分を目安に用意し、主食・副菜・おやつをバランスよくそろえましょう。また、ローリングストックを取り入れて常に新しい状態を保つことがポイントです。家族の状況に合わせた工夫をしながら、安心できる備えを整えていきましょう。